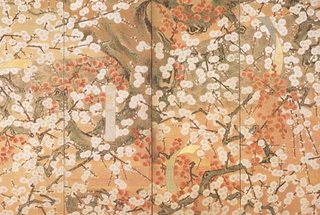若冲展をみに上野へいく。
平日だけど、とても混でた。
「鳥獣花木図屏風」を3年ぶりぐらいにみる。
いつみてもポップな感じがする。
家に昔ハピネス展で買った「鳥獣花木図屏風」の
巨大ポスターが貼ってあって、
毎日見ているせいか、
今回はニワトリたちに目がいく。
若冲の描く生き物は、生命の「存在」に触れている、とよくいうけれど、
若冲のニワトリが、
小学校の飼育委員で毎朝世話してたニワトリよりも、
「ニワトリ」に見えるこの感じはなんなんだろう?
ラマチャンドランが「脳のなかの幽霊、ふたたび」で、
セグロカモメのヒナは、
親鳥の黄色のくちばしの先についている赤い斑点に反応して、
餌くれとつつくんだけれど、
全然くちばしに似てない、
赤色の線を3本引いた黄色の棒をヒナに見せたところ、
本物のくちばし以上にヒナはそれをつっついた!!
という話を紹介していて、
それを、くちばしを超えたくちばしという意味で、
「スーパーくちばし」と呼んでいた。
セグロカモメのヒナにとっては、赤色の3本線つきの黄色の棒が、
「スーパーくちばし」
であったように、
ヒトの脳にとって、若冲の描いたニワトリは、
「スーパーにわとり」
なのだろうか?
「紅白梅図屏風」に意図せずに足がとまった。
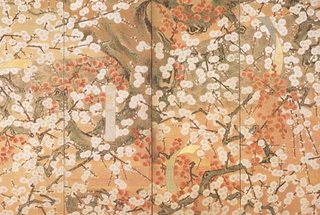
ありえない数の白色の梅の花が、屏風一面に咲き乱れていて、
それらが、あさ日から夕日までをイメージした1日の光の変化に
合わせて、いろいろな表情をみせる。
説明文には、作者不詳で、春の歓びをあらわしている、とかいてあった。
思考とは関係なしに、目が喜んでいる、という感じがして面白かった。
見ていると心が動かされて、それでずっと見入ってしまう感じ。
ふと、この感覚を絵なしで言葉だけで伝えることはできるのだろうか?
と思う。
屏風一杯に咲き乱れるように分布する白い梅の花のパターンが
脳に入力されると、 圧倒的な並列性をもった視覚システムは、
「花」という認識を成立させるほかに、 屏風のグローバルな
パターンから、 ある未知の抽象的なパターンも抽出している。
その未知の抽象的なパターンは、快感を引き起こす情動システムに
直結していて、 その結果、脳はそれを見ているだけで
「嬉しい」という感覚を引き起こす・・・
と脳科学的に表現してみても、きっとなにも伝わっていなくて、
問題は、
絵の「パターン」をどうすれば視覚的に描写できるのか?
それによって、読む人の脳にも、
その「未知の抽象的なパターン」なるものを引き起こすことはできるのか?
がポイントで、
これを、「目の喜びを言葉で伝える問題」と名付けよう。